中陰法要
故人が亡くなられてから49日の間、7日毎にお勤めいたします。


葬儀(お葬式)とは、葬場で故人のご遺族等が集まって行う勤行です。
故人を葬るにあたって行われる、一連の法要や儀式のことを葬送儀礼といいます。いずれも故人の往生をご縁として仏法に遇い、故人も遺った方も阿弥陀さまにひとしく摂め救いとられている恩徳に報謝する仏事です。
所属寺院がある場合は、宗派・寺院名・連絡先を把握しておき、可能であれば、事前に住職と葬儀について、相談しておきましょう。
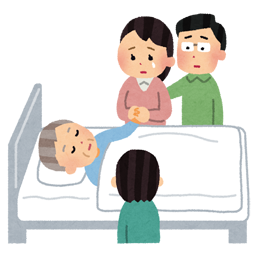
大切な儀式を依頼するわけですから、信頼できる寺院を探すことが重要です。葬儀社からも紹介を受けることができますが、手数料を取られないことの確認をしましょう。
※当寺門信徒の方が公益社 天神橋会館または花熊フローベアホールでの葬儀を希望される場合は、葬儀社様へ直接ご依頼いただいても差し支えございません。

良い葬儀社とは、ご遺族の気持ちを「聞く力」を持ち、限られた予算の中で、故人の尊厳を損なうことなく、様々な配慮ができるところといえるでしょう。
あらかじめ葬儀社の情報を調べておくのも大切です。ただしその際、インターネットの口コミや広告の情報だけに頼るのは危険です。
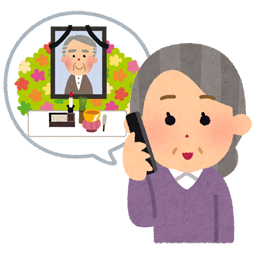
本来は命終に臨む本人が、阿弥陀さまへの報恩感謝の儀式として行う勤行ですが、多くの場合、命終の後に故人に代わって僧侶と故人のご家族等でお勤めいたします。勤行はご本尊の前で行い、その場所が故人の枕元にあたる場合が多いことから、枕経といわれることもあります。ご希望により、通夜勤行と併せてお勤めする場合もあります。
次第
どのような葬儀にするか寺院・葬儀社等とよく相談し、葬儀本来の意義を損なうことのないようにしましょう。
葬儀内容を打ち合わせるとき、葬儀社にご遺族の意思と予算をきちんと伝えましょう。特に必要のないオプション等は要注意です。
故人生前の葬儀に関する要望にしばられすぎないようにしましょう。大切なのはご遺族の思いです。

葬儀の前夜に、ご遺族等が仏前に集まって行われる勤行です。
次第
本来は故人の棺をご自宅から葬場へ送り出す際に、ご自宅に安置されているご本尊を前に行う勤行ですが、多くの場合、葬場勤行と併せてお勤めいたします。
次第
葬場でご遺族等が集まって行われる勤行です。葬場勤行は「葬儀」ともいいますが、浄土真宗では「告別式」とはいいません。本願寺派では、蓮如上人の頃から「正信念仏偈」の勤行が用いられています。
次第
火葬場で火葬の前に行う勤行です。
次第
収骨の後に行う勤行です。初七日の中陰法要を繰り上げて併修する場合もあります。
次第
本来は納棺時に納棺勤行、収骨時に収骨勤行を行います。(ご希望によりお勤めいたします)
浄土真宗本願寺派での正しいお焼香の作法は、お香を額におしいただかず、回数は1回です。
生前に帰敬式を受式されていない場合は、住職が本願寺住職(ご門主さま)に代わって棺の中の故人に対して剃髪式(おかみそり)を行い、法名を授与いたします。浄土真宗では法名といい、戒名とはいいません。院号は宗門より授与いただくものです。
浄土真宗での葬儀は、故人のために善事を行う追善回向の仏事や、僧侶が引導を渡す儀式ではなく、ご遺族等が相集い、お念仏を申して故人に哀悼の意を表しつつ、人生無常の道理を聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。
浄土真宗本願寺派における葬送儀礼の流れや、葬儀をするにあたり後悔しないヒント等についてご説明しています。
浄土真宗の葬儀の中で大切にされてきた「死を受け容れていく心」をテーマとして、大切な方を看取った人の話等を紹介しています。